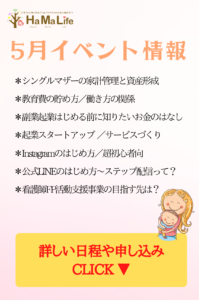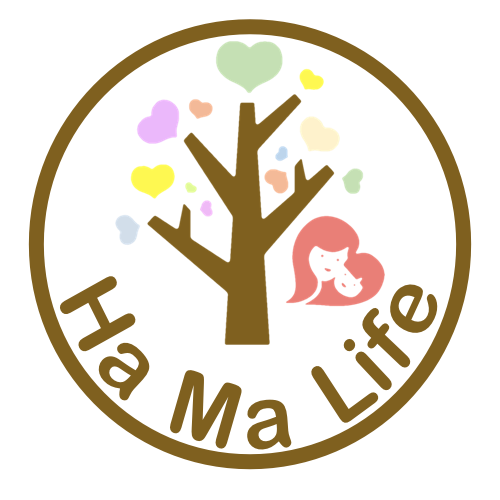今回は離婚相談でもよく聞かれるテーマ、財産分与について書かせていただきます。
「いったいどこからが財産分与対象なの?」と「財産はどうやってわけるの?」と分けるべき対象がどこからどこまでなのかがわからない。というケースや、実は勘違いをし、分けなくていいものまで分けて、損していたというケースもあります。
離婚後に後悔しないためにも、対象となる財産や財産分与割合はあらかじめ知っていてもらいたいところです。
財産分与で後悔したこと
私自身、離婚のときは弁護士などに相談するわけでもなく、協議離婚だったので財産分与についても、なんとなく分けました。
どこからどこまでが対象になるとかも、あまり深く考えずに基本にのっとりおおよそ1/2になるように分けたのですが、
離婚後に
「あれも分けておけばよかった…。」
「パソコン使っていないなら私がもらっておけばよかった…。」
「カーローンは先に支払っておけばよかった」
などと、実は色々後悔したんです。
でも、離婚した後からの話し合いって、やっぱりうまくいかないんですよね。
だからこそ、まずは最低限、財産分与の対象となる範囲を知っておくことが大事です。
<財産分与は3つの種類に分けられる>
3つの意味合いで財産分与があります。
- 清算的財産分与
婚姻期間中(結婚生活の中で)に築き上げてきた預貯金や金融資産、不動産などの財産を分ける
- 扶養的財産分与
離婚後の困窮した状態を防ぐため生活費の負担をしてもらう
- 慰謝料的財産分与
傷つけた相手に対して精神的苦痛に対する損害賠償
皆さんがよくイメージしているのは①の清算的財産分与です。
この財産分与は結婚してから夫婦で築き上げてきた財産を分けることをさしますが、財産には夫婦の共有財産と、個人的な財産である特有財産があるということに注意しましょう。
財産分与の対象は共有財産となり、財産分与割合は基本的に1/2ずつとなっています。

ただし、話し合いでこの1/2という分与割合を変えること自体は問題ありません。
まずは、財産を書き出すことからはじめましょう。
財産分与割合は基本的には1/2。でも例外もあり。
共有財産は結婚してから離婚まで、また別居するまでの期間に夫婦で築き上げた財産を指します。
家事育児をして働いていなくても、家のことをやっていたおかげで夫が働けたという事でもあるため、夫の収入で買ったものも共有財産としてみなすことができます。また、家事育児は肉体労働ではありませんが、感情労働です。報酬は発生しませんが肉体労働以上に神経をすり減らし、疲労も大きいもの。育児は仕事という視点でも客観的に考えてみるとよいでしょう。
しかし、共働きでもともと会計が別になっている場合や、お互いが自営業の場合などでは財産分与が発生しないこともあります。
協議離婚であれば、お互いが納得すればOKですので、財産分与の範囲を明確にしておくことが重要です。
さらに、会社経営者や弁護士、医師など特別な才能・資格を持っているケースでは、結婚以前の努力によって収入が高くなっていることを考慮すると、完全に1/2ずつの分与とならないこともあります。また、会社名義の資産に関しては財産分与対象となりません。
逆にこのルールを活用して、意図的に会社の口座に財産を移すケースもあるため、経営者の旦那さんの場合は注意しておきましょう。
財産分与で揉めそうな場合は、弁護士へのご相談をオススメいたします。
共有財産と特有財産の違い
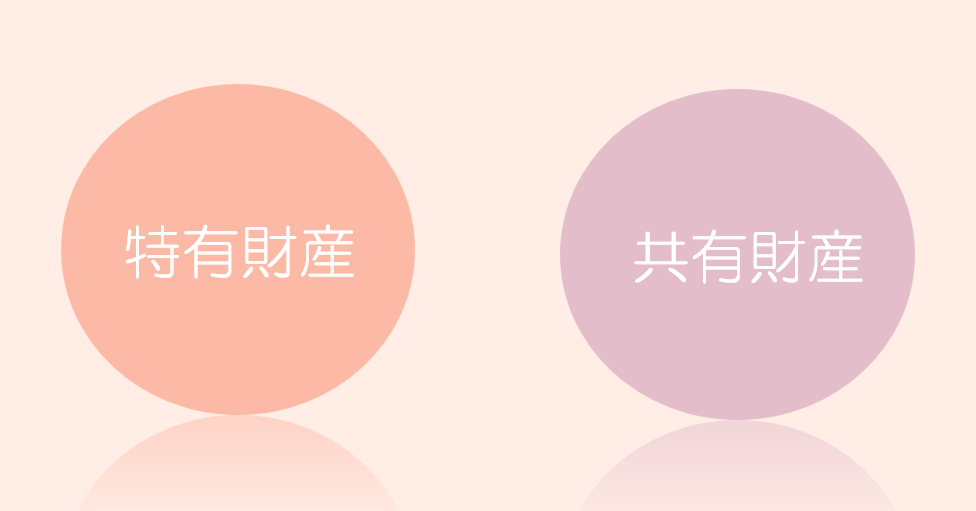
共有財産とは
結婚してから離婚(別居)するまでに作った財産ですが、財産には預貯金以外にも、下記のようなものが含まれます。
・現金
・預貯金
・保険、金融商品
・家具家電
・自動車
・不動産(持ち家など)
・年金
・ローン、借金
など
プラスの財産もマイナスの財産も分けることになるため、住宅ローンや車のローン、そのほか借金などがあった場合、こちらも分けていく必要があります。
私の場合、ここがとてもややこしく失敗した部分でもありました。
車のローンは、元夫が車を引き取るため、ローンの支払いもそのまま元夫が続けることになったのですが、実はローンの名義は私の名前だったんですよね。ただ、ローンの名義変更は基本的にはできないため、私がローンの返済を続け、養育費とともに車のお金も一緒に振り込んでもらっていました。
ただ、すぐに返済が滞ったんです。
でも、信用情報に傷がつくのは車を使っていない私です。このようなこともあるため、ローン関係の財産分与は気を付けないと後々後悔してしまうのです。
幸いにも私の場合、義父あてにローンの返済を一括でお願いする手紙を出し、すぐに完済することができました。
離婚するときはかんたんに、考えてしまいましたがリスクがとても大きいので、離婚前にしっかり話し合っておくべきでした。
個人の特有財産とは
独身時代から築いてきた財産や、自分しか使っていないようなものが対象になります。
具体的には下記を参照ください。
◎独身時代に手に入れた財産
現金・預貯金
株・債権
不動産
自動車
家電・家財道具
積立型保険
私的年金
借金
将来の退職金
◎個人で築いた財産
独身時代に行った投資の配当金
独身時代の財産で婚姻期間中に行った投資の配当金
趣味やギャンブルなどで作った借金
◎自分しか使わない家財
男女の区別がある服飾品
スマートフォン
洋服
日常的に消費されてしまうもの
◎相続した財産
現金・預貯金
株・債権
不動産
自動車
骨董品・美術品
借金
など
書くと簡単に見えますが、悩みやすいポイントとしては、元々自分が貯金していた銀行口座をそのまま結婚後にも使用していた場合でしょうか。
結婚する前まで貯まっていた分は特有財産とすることができます。ただし、難しいのは結婚する時点でどれくらいの財産があったのか証明できるかどうか?です。通帳などに記録して残してあれば、ここまでは自分の財産だったと主張できますが、証拠がないと共有財産とみなされてしまう可能性もあるため、注意しましょう。
銀行など金融機関窓口で、過去の預金記録を出してもらうこともできます。ただし、取引記録の保存を義務付けられているのは10年間ですが、開示するかどうかは別問題で、銀行ごとにいつまでさかのぼって開示してくれるか異なるため、婚姻期間が長いケースでは証明が難しくなってしまいます。
単純なケースでは
独身の頃、預金が200万円ありました。
そのままその口座を活用して、離婚するときには800万円に増えていたとすると、
特有財産は200万円。
共有財産は800-200=600万円。
財産分与をすると、特有財産200万円+共有財産300万円で500万円を残して離婚することが可能です。
共有財産と特有財産を意識しないと単純に800万円を1/2して400万円となってしまいます。100万円損してしまうので、共有財産と特有財産の線引きは意識しておくとよいでしょう。
金融資産以外のモノはどう分ける?
預貯金などの金融資産や、保険などは金額という数字で評価ができるため分けやすいですが、持ち家や自動車、家具家電などモノを分けることはとても難しいです。
お互いが合意すれば必要なものをそれぞれが受け取る形でもよいでしょう。
揉めそうな場合は、物的資産も評価額などを出し、数値化しておくと分けやすくなります。
作成したエクセルシートをPDFにしましたので、財産分与割合を考える際に、印刷・記入してお使い下さい。
何事も見える化することで、お金も頭の中が整理されていきます。
ぜひ離婚が頭によぎったときには、書き出してみましょう。
今回は財産分与について、基本的な分け方のお話をさせていただきました。
共有財産と特有財産をしっかり分けて考えることを意識してくださいね。
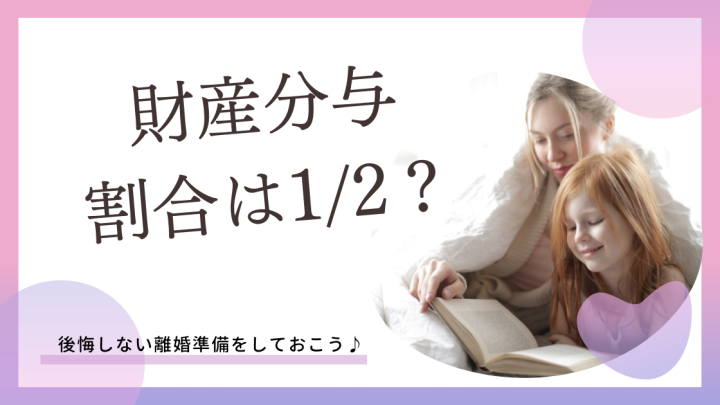
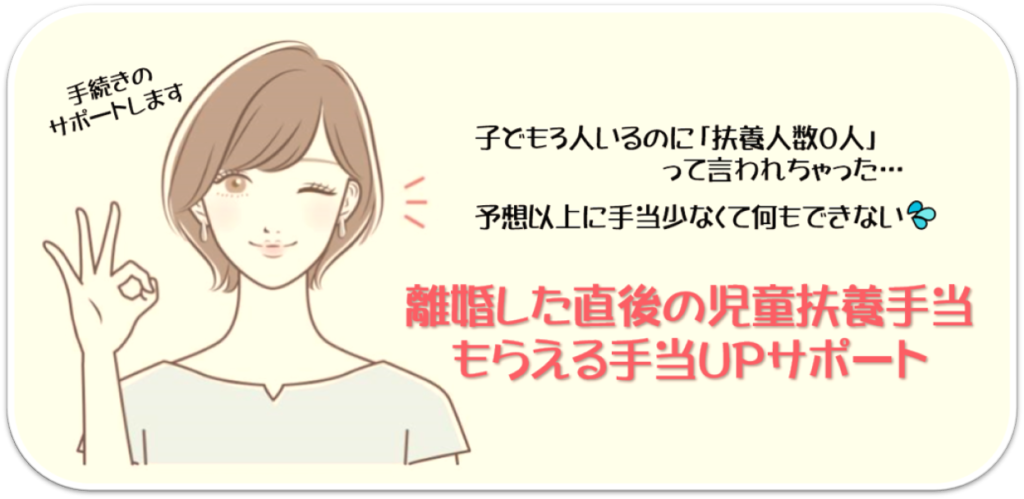







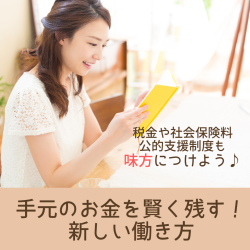



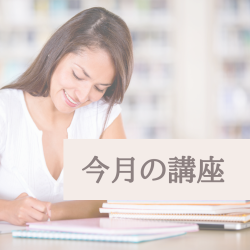
_1125×1694-199x300.jpg)